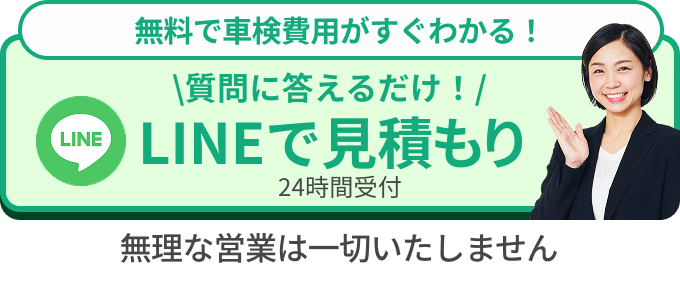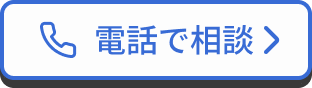「自動車重量税ってなに?」
「重量税っていつ払うの?」
「どれぐらい払えば確認したい…」
上記のような疑問・お悩みをお持ちではないでしょうか?
自動車重量税は車両の重量・新規登録からの経過年数によって金額が変わる国が定めた税金で、重量税と略して呼ばれるのが一般的です。
ただ、詳細な料金・支払うタイミングなどが分からない方は多いと思います。
そこで当記事では、自動車重量税の基本・金額・いつ支払うのかについて詳しく解説していきます。
また、以下の内容についても解説していきます。
- 車検時の重量税の簡単な調べ方
- 重量税の還付制度・申し込み方法について
- 車検時の重量税に関するよくある質問
車の重量別の重量税の金額一覧表も掲載しているので、ご自身がいくら支払う必要があるのかを詳細に確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
車検費用が気になる方は、10秒でできる無料の「かんたん料金シミュレーション」で、車検費用の目安をチェックしましょう。
モビフル車検なら、よくある部品交換43項目がすべて追加料金なし!見積もり通りの金額で受けられるから安心です。
車検時の自動車重量税とは
自動車重量税は車の重量・経過年式などによって金額が変わる税金のことです。
金額はあらかじめ国によって決められており、車の状態・不具合があるかどうかなどは金額に影響しません。
重量税は支払う金額を事前に把握できるため、支出管理がしやすいというメリットがあります。
支払う金額の詳細は後ほど解説していきます。
参考資料:自動車重量税のあらまし(国税庁)
重量税だけでなく、車検費用の全体像・リアルな金額相場が知りたい方は以下を参照ください。
なお、来店不要でお家で完結できるモビフル車検なら、見積もりから追加費用が99%発生しないのでおすすめです。
まずは10秒でできる無料の「かんたん料金シミュレーション」をぜひお試しください。

重量税を支払うタイミング
重量税は主に自動車検査(車検)時に支払います。大きく分けて以下の2種類があります。
- 新規検査時(新車購入時に受ける初回の車検) ⇒次回の車検が3年後なので、3年分の重量税を一回で支払います。
- 継続検査時(2回目以降の車検) ⇒継続検査は2年ごとに受けるので、一回で2年分の重量税を支払います。
支払うタイミングによって上記のような違いがあるので、初めて新車購入を検討している方・継続検査が初めての方は念頭に置いておきましょう。
自動車重量税の金額を決める4つの要素
続いて、自動車重量税の金額を決める主な要素について解説していきます。
以下は、重量税の金額にかかわる主な要素です。
- 車両重量
- 車両区分(軽自動車・普通車など)
- 車の使用年数(13年・18年超過で税額アップ)
- エコカー減税対象車かどうか
ご自身が払う重量税がどれぐらいになるのか見積もる際に、非常に重要な要素になるので把握しておきましょう。
それぞれ順番に解説していきます。
車両重量
自動車重量税の金額に最も影響するのは、車の重量です。
国土交通省が発表している資料では、500㎏~3,000㎏までの重量区分が設定されており、それぞれ金額が大きく異なります。
また、車両重量1,501㎏から1㎏でも減れば、違う料金区分になります。
上記のように、車両重量による料金区分はしっかり決められていることを念頭に置いておきましょう。
車両区分(軽自動車・普通車など)
車種によっても重量税は大きく変わります。
一般的に使用される車両は普通車・軽自動車の2つに分類され、それぞれ重量税の金額設定が違います。
普通乗用車(小型車含む):重量の区分が多く、重量が増えるほど重量税が増額します。
軽自動車:料金区分が1つしかなく、普通乗用車と比べて安い。
※軽自動車はサイズ・最大積載量に関する規定があり、車両自体の重量に関する規定はありません。
上記のように、車両区分も金額に大きく影響することを把握しておきましょう。
車の使用年数(13年・18年超過で税額アップ)
車の使用年数(新規登録からの年数)も重量税の金額に影響します。
新車登録から13年・18年以上経過した自動車は重量税が増額されます。
以下の、2010年10月に新規登録した車の重量税が増額されるまでの流れを例に解説していきます。

参考資料①:租税特別措置法第九十条の十一のニ(出典:財務省)
参考資料②:租税特別措置法第九十条の十一の三(出典:財務省)
参考資料③:新車新規登録から13・18年経過する自動車の経過年数の数え方(参考)(出典:国土交通省)
重量税が増額されるのは「初回車検から12年11か月経過」以降に車検を受けるタイミングです。
※軽自動車は「13年経過後の12月以後に車検を受けたとき」に増額されるため、普通乗用車と増額のタイミングが異なります。
エコカー減税対象車かどうか
車検を受ける車がエコカーかどうかも車検時の重量税に大きく影響します。
エコカーに対して、重量税が免除・減税される制度があります。
小型含む普通乗用車のエコカーに適用の減税率:免税もしくは50%・25%減税
軽自動車のエコカーに適用の減税率:免税もしくは75%・50%・25%減税
参考資料①:エコカー減税 (自動車重量税) の概要(出典:国土交通省)
参考資料②:2023年5月1日からの自動車重量税の税額表(出典:国土交通省)
車検費用は重量税が占める割合はとても大きいので、減税によって支払額は大きく変わります。
【エコカー減税率に関して】
エコカー減税は、排出ガスが少ない・燃費性能がいい車に対して重量税の税率を減免する措置のことです。
エコカー使用者で減税額を知りたい場合:エコカー減免対象 重量税の検索(出典:ヘルムジャパン)
減税率は目標平均燃費(25.4km/L)の達成率に応じて変化するようになっており、以下のように区分されています。
▼適用車両
- ハイブリッド車
- ガソリン車
- クリーンディーゼル車
- 電気自動車
| 期間別の減税率 | ハイブリッド車・ガソリン車・グリーンディーゼル車の燃費達成率 | 電気自動車 | ||||||||
| 60% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100~125% | |||||
| 2024年1月~2025年4月の 減税率 | 軽減なし | ▲25% | ▲50% | 免税 |
免税 | |||||
| 2025年5月~2026年6月の 減税率 | 軽減なし | 本則税率 | ▲25% | ▲50% | 免税 | |||||
参考資料:2030年度の燃費基準(国土交通省)
【一覧表】車検時の自動車重量税はいくら?
車検時に支払う重量税を車両重量・車種・エコカーの場合などもふまえて、金額一覧表を作成しました。
以下の2つの料金一覧を確認していきます。
- 乗用|3年自家用
- 乗用|2年自家用
それでは順番に確認していきましょう。
乗用|3年自家用
3年分の重量税を支払うのは、基本的に初回の車検時です。
それでは、3年自家用(初回の車検時)の重量税の金額を確認していきましょう。
【3年|自家用乗用車の重量税一覧】

参考資料:2023年5月1日からの自動車重量税の税額表(出典:国土交通省)
3年分の重量税を支払うのは初回車検の1回のみとなります。
初めて新車購入を検討している方は参考にしてください。
乗用|2年自家用
普通乗用車の場合、2回目以降の車検は2年ごとに行い、2年分の重量税を支払います。
そのため、車検時は主に以下の重量税額を支払うことになります。
【2年|自家用乗用車の重量税一覧】

参考資料:2023年5月1日からの自動車重量税の税額表(出典:国土交通省)
※上記は自家用の軽・普通乗用車の重量税額です。車両区分・車両の用途などで重量税額は異なります。
車検時の重量税を簡単に調べる方法
次回車検時に支払う自動車重量税を簡単に知りたい場合は、以下の料金検索サイトで調べる方法がおすすめです。
普通車の重量税を調べたい場合: 次回自動車重量税紹介サービス(国土交通省)
軽自動車の重量税を調べたい場合: 次回自動車重量税照会サービス(軽自動車検査協会)
以下の情報を入力することで、次回車検時に支払う重量税を確認することが可能です。
【照会サイトでの入力事項】
- 車検証に記載の車台番号
- 次回の車検予定日
上記入力後、照会ボタンを押すことで次回車検時に支払う重量税が確認できます。出費の目安として、ぜひ確認しておきましょう。
廃車時の重量税還付制度に関して
重量税還付制度が適用されれば、支払った重量税の一部が返ってくる可能性があります。
廃車時に車検の有効期限が残っていた場合、車検有効期限に応じた自動車重量税の還付を受けられます。
申請は運輸支局にて、一時抹消の解体届出と永久抹消登録の申請と同時に行います。
受け取れる金額は、廃車時点の車検の残り期間により異なりますが、2年分の重量税はかなり高額なので、受け取るようにしましょう。
還付金を受け取るには以下の条件をクリアする必要があります。
- 解体を理由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局に提出すると同時に、還付申請書を提出したものであること
- 車検の残存期間が1か月以上であること
参考資料:使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度(出典:国税庁)
また、還付申請の前に以下の4つのポイントを抑えておくようにしましょう。
- 還付金額の計算方法
- 自動車重量税の還付申し込み方法
- 還付金の受取方法
- 還付金の受け取り方法
それぞれ順番に解説していきます。
還付金額の計算方法
重量税の還付金額は「納付した重量税×車検の残り期間÷車検の有効期限」で求められます。
例えば、継続検査時に納付した重量税が24,600円(24か月分)で、残りの車検期間が12ヵ月の場合で計算してみましょう。
「24,600×12÷24=12,300」と、還付金額は12,300であると求めることが可能です。
上記のように、廃車時における還付金額を申請前に見積もっておきましょう。
自動車重量税の還付申し込み方法
続いて、還付金の申し込み方法について解説していきます。
先述の通り、還付申し込みは永久抹消登録・解体届出と同タイミングで申請します。
申し込みの流れは以下の通りです。
- ディーラー・リサイクル業者などに車を引き取ってもらう
- 業者から車を解体した旨の連絡を受ける
- 永久抹消登録・解体届出書と一体になった還付申込書に必要事項を記載する
- お近くの運輸支局に書類を提出する
【還付申込書の記入例】
▼普通車の場合

▼記入方法
- 申請者(所有者)の「氏名又は名称」「フリガナ」記入
- 申請者(記入者)の住所()住所コードを入記入(個人は住民票の住所、法人は登記上の本店所在地)
- 日中連絡可能な電話番号を記入
- 申請者所有者コードを記入
- 申請者(所有者)の個人・法人番号を記入
- 還付金の振込口座情報を記入
- ゆうちょ銀行の場合は0を記入
- 永久抹消登録申請の場合は実印を押印
参考資料:自動車重量税還付申請書記載のポイント(国税庁)
※代理人が申請する場合は申請者(所有者)が実印を押した委任状が必要になります。後述の記入例を参考にしてください。
▼軽自動車の場合

▼記入方法
- 申請者(所有者)の「氏名又は名称」「フリガナ」記入
- 申請者(記入者)の住所()住所コードを入記入(個人は住民票の住所、法人は登記上の本店所在地)
- 日中連絡可能な電話番号を記入
- 申請者所有者コードを記入
- 申請者(所有者)の個人・法人番号を記入
- 還付金の振込口座情報を記入
- ゆうちょ銀行の場合は0を記入
- 申請者(所有者)と届出者が同じであっても両方に記載をする
参考資料:自動車重量税還付申請書記入のポイント(出典:国税庁)
※代理人が申請する場合は申請者(所有者)が実印を押した委任状が必要になります。後述の記入例を参考にしてください。
また、還付申請書の審査・手続きは時間をかけて行うため、還付金受取までに時間がかかることも念頭に置いておきましょう。
廃車から還付金受取で大体2~3ヶ月ほど時間がかかります。
還付申し込みに必要なもの
先述の還付申請書と合わせて、以下のものが必要になります。
- 車の所有者の実印か認印
- 実印の印鑑証明書
- 身分証明書
※車の所有者以外が申請する場合は、所有者本人のサイン・押印がされている委任状も必要になります。
【重量税還付申し込み時の委任状の記入例】

参考資料:使用済み自動車に係る自動車重量税還付申込書の記載(出典:国税庁)
※委任状は車の所有者の本人が記入するようにしましょう。
還付金の受け取り方法
申請受理後に重量税還付金を受け取る方法は以下の2つです。
- 預金口座へ振り込んでもらう
- 最寄りのゆうちょ銀行で受け取る
参考資料①:使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について(出典:国税庁)
参考資料②:預貯金口座への振込みによる方法(出典:国税庁)
振り込みによる受取は手間もかからず非常に便利なので、ぜひ利用してみてください。
※預金口座への振り込みは、還付申込書に預金口座の情報を記載する必要があります。
還付金を受け取る際の注意点
重量税の還付申し込みに関して、以下の3点に注意する必要があります。
- 永久抹消・解体届出と同時に還付申請する必要がある
- 自動車売却の場合は還付金は受け取れない
- 重量税還付は車の最終所有者が受け取れる
特に1つ目に関して、還付申請をするタイミングは運輸局で廃車手続きをするタイミングでのみ行えます。
後日申請は受け付けてくれませんので、永久抹消・一時抹消・解体届出と同時に申請するようにしましょう。
車検時の重量税に関するよくある質問
車検時の重量税に関して、特に多く寄せられていた質問に回答していきます。
以下の質問が特に多数でした。
- 身体障がいがある場合は重量税は免除されますか?
- 重量税と自動車税は同じですか?
それぞれ順番に解説していきます。
障がいがある場合は重量税は免除されますか?
重量税は減免されませんが、自動車税は減免される可能性があります。
減税措置の対象車は、以下の2つのケースで適用されます。
- 「障がいを持つ方」が運転する自動車
- 「障がいがある方と生計を同じくしている方」が運転する自動車
【減税の適用条件】
上記の2つのケース別に適用条件を紹介していきます。
▼1の適用条件
「車の使用者本人が身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付されている」
▼2の適用条件
- 車を障害のある人の通院や通学などのために使用する
- 車の使用者と障がいのある方が同居している
※減税が適用される障がいの程度・生計を同じくする人の定義は各市区町村によって異なります。役所・役場に問い合わせて「税金に関する窓口」につないでもらいましょう。
【減税額の上限】
自動車税種別割の減免上限額:45,000円
※自動車税が45,000円以下の場合は免税になり、45,000円超えであれば差額分を納付することになります。
重量税と自動車税は同じですか?
重量税と自動車税は全く異なる税金です。
重量税は車両重量によって金額が変わり、車検時に支払う税金で、車検が2年ごとであれば、2年に1回支払う必要があります。
これに対して、自動車税は車の排気量によって金額が変わり、毎年支払う必要のある税金です。
それぞれ別の税金なので、混同しないように注意しましょう。
まとめ
内容を簡単におさらいしていきます。
自動車重量税とは「車の重量・経過年式などによって金額が変わる税金のこと」です。
金額は国によってあらかじめ定められているため、支払う金額を事前に確認でき、支出監理がしやすいです。
【重量税を支払うタイミング】
- 新規検査時(新車購入時に受ける初回の車検)
- 継続検査時(2回目以降の車検)
新規検査時の重量税:次回の車検が3年後なので、3年分の重量税をこの時点で支払う
継続検査時の重量税:基本的に2年ごとに受けるので、1回の車検で2年分支払う
上記のように支払うタイミングに違いがあるので、初めて新車購入をする方・継続検査が初めての方は念頭に置いておきましょう。
【自動車重量税の金額を決める4つの要素】
重量税の金額は以下の4つで決まります。
- 車両重量
- 車種(軽自動車・普通車など)
- 車の使用年数
- エコカー減税対象車かどうか
続いて、車検時の自動車重量税の金額を再確認していきましょう。
続いて、次回車検時の重量税を簡単に調べる方法を再確認していきましょう。
ご自身が支払う重量税額を調べるには、以下の2つが簡単でおすすめです。
情報を入力・照会ボタンを押すと金額が表示されます。次回車検時の出費の目安として確認しておきましょう。
【廃車時の重量税還付制度に関して】
廃車として引き渡した車に車検の有効期限が残っていた場合、その有効期限分の重量税が返ってくる制度です。
申請は各運輸支局にて、一時抹消の解体届出・永久抹消登録の申請と同時に行います。
▼還付を受ける条件
- 解体を理由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局に提出すると同時に、還付申請書を提出したものであること
- 車検の残存期間が1か月以上であること
【還付金額の計算方法】
車検時の支払った重量税額×車検の残り期間÷車検の有効期限で還付金額を算出することが可能です。
直近の車検時に重量税24,600円支払い、残りの車検期間が12ヵ月の場合「24,600×12÷24=12,300円」となります。
上記のように還付金額を求めることができるので、申し込みを検討している方は事前に金額を確認しておきましょう。
【重量税還付の申し込み方法】
- ディーラー・リサイクル業者に車を引き取ってもらう
- 業者から解体が完了した旨の連絡を受ける
- 永久抹消登録・解体届出書と一体になった還付申込書を記入する
- お近くの運輸支局に書類を提出する
※上記提出書類の審査・手続きは時間を要するため、還付金のすぐに受け取ることはできません。上記の手続きには大体2~3ヶ月ほどかかります。
【還付申し込みに必要なもの】
- 車の所有者の実印か認印
- 実印の印鑑証明書
- 身分証明書
- 委任状(車の所有者以外が申請する場合のみ)
▼委任状の記入例

※委任状は車の所有者本人が記入するようにしましょう。
【還付金の受け取り方法】
- 預金口座へ振り込んでもらう
- 最寄りのゆうちょ銀行で受け取る
申請時に口座情報を記入する必要がありますが、手間がかからない預金口座への振り込みがおすすめです。
【還付金を受け取る際の注意点】
- 永久抹消・解体届出(廃車手続き)と同時に申請する必要がある
- 自動車売却の場合は申請できない
- 還付金は車の最終所有者のみが受け取れる