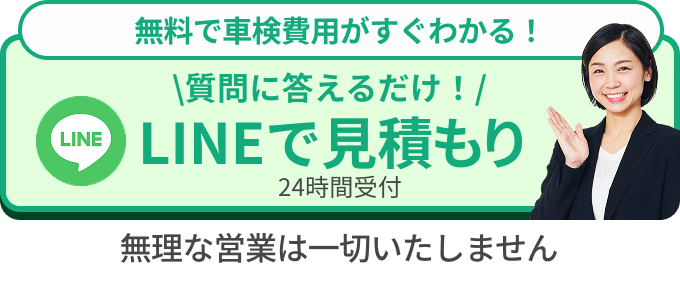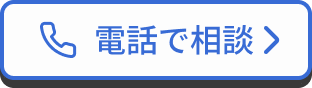「8ナンバーの車検費用は?」
「車検期間に違いはある?」
「普通車と何が違うか知りたい…」
上記のような疑問・お悩み、お持ちではないでしょうか?
8ナンバーに変更すると車検費用が安くなると聞いて、利用を考えている方も多いと思いますが、実際の費用感や普通車との違いが分からない方も多いと思います。
そこで本記事では、8ナンバーの車検について徹底的に解説します。
また比較表を使って、普通乗用車の車検費用とどれぐらい差があるのかも解説。
さらに、以下の内容も紹介していきます。
- 8ナンバーにするメリット・デメリット
- 8ナンバー取得までの流れ
- 8ナンバーの車検のよくある質問
8ナンバーへの変更を検討している方、現在利用中の方も、ぜひ参考にしてください。
車検費用が気になる方は、10秒でできる無料の「かんたん料金シミュレーション」で、車検費用の目安をチェックしましょう。
モビフル車検なら、よくある部品交換43項目がすべて追加料金なし!見積もり通りの金額で受けられるから安心です。
8ナンバーの基本知識
8ナンバーは「特殊な改造をほどこした車両」に割り当てられるナンバーのことです。
そのため、8ナンバーをつける車両は「特種用途自動車」と呼ばれます。
改造とは、カーゴ部分(後部座席部分)にベッドスペースが設置されていたり、放水するためのタンク・ホースが装備されていたりすることなど、様々です。
改造の内容は車両の用途によって大きく異なり、緊急時での使用、法令で定めた事業での使用、これら以外の用途の3つに分類されます。
具体的には、以下の車両が8ナンバーに分類されます。
- パトカー・救急車・消防車などの緊急車両
- キャンピングカーなどの家庭でも使用する車
- 医療・介護用の寝台車両
- その他(キャンピングカー・霊柩車) など
8ナンバーに該当する車両の詳細は国土交通省による「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の中の4 特種用途自動車等から確認可能です。
(出典:国土交通省)
8ナンバーの車検期間は2年
8ナンバーの車検は初回を2年後、それ以降も2年ごとに受ける必要があります。
普通乗用車(3ナンバー・5ナンバー)の場合、初回の車検は3年後、それ以降は2年ごとと、初回の車検期間のみ8ナンバー車と異なることが分かります。
8ナンバーの用途自体は特殊ですが、車検期間に関しては、通常とあまり変わらないので、車検に手間がかかるなどのデメリットは少ないです。
ただし、8ナンバーで重量が8t以上の車両は、1年ごとの車検になるので注意しましょう。
【比較表】8ナンバーと普通乗用車(3ナンバー車)の車検費用
続いて、8ナンバーと普通乗用車(3ナンバー車)の車検費用を比較していきましょう。
金額は以下の通りです。
| 費用種類 | 車両重量 | 8ナンバー | 自家用乗用車 |
|---|---|---|---|
| 法定費用 | 軽自動車 | 21,290円 | 25,940円 |
| ~500㎏ | 29,980円 | 27,650円 | |
| ~1,000㎏ | 35,850円 | ||
| ~1,500㎏ | 38,180円 | 44,050円 | |
| ~2,000㎏ | 52,250円 | ||
| ~2,500㎏ | 46,380円 | 60,450円 | |
| ~3,000㎏ | 68,650円 | ||
| 整備費用 | 軽~3,000㎏ | 50,000~120,000円 | 40,000~100,000円 |
| 合計 | 軽~3,000㎏ | 71,290~166,380円 | 65,940~168,650円 |
※重量税・自賠責保険料は、2年分を想定して算出しています。
※指定工場で車検受けた場合を想定しています。(検査手数料1,800円に統一)
8ナンバーは普通乗用車より法定費用が安く設定されています。
しかし、特殊設備の維持・修理などで、整備費用が高額になる可能性が高いです。
8ナンバーと自家用乗用車の合計金額の差はほとんどなく、費用感はあまり変わらないといえます。
また、8ナンバーの車検費用の内訳には、以下の項目が含まれています。

- 整備費用(車検基本料・部品代金・工賃)
- 自動車重量税(重量税)
- 自賠責保険料
- 印紙代(各種手数料)
大きく分けて、この4つが8ナンバーの車検費用に含まれており、普通乗用車の車検と払う項目は一緒です。
それぞれの金額はいくらか、普通乗用車と比較して安いのか・高いのかを詳しく解説していきます。
整備費用は高額になりやすい
8ナンバー車は構造が特殊なので、一部の車検業者しか整備に対応できず、車検基本料金を割高に設定されているケースもあります。
整備料金が高いのは、キッチン・水道・ベッドなどの特殊設備のメンテナンスにコスト・手間がかかるためです。
もちろん、通常の車検整備と同様に、車のサイズ・コンディションによっても金額が上下します。
金額面に不安がある方は、複数の車検業者に見積もりを出してもらい、大体の費用感を把握するようにしましょう。
重量税は安く抑えられる
8ナンバーの重量税は、普通乗用車よりも安く設定されています。
安くなる主な要因は、8ナンバーの重量税の最大金額が低いためです。
以下は、8ナンバーと普通乗用車の重量税の金額比較表です。
| 重量区分 | 8ナンバー | 自家用乗用車 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 8,200円 | 4,100円 |
| ~500㎏ | 8,200円 | |
| ~1,000㎏ | 16,400円 | |
| ~1,500㎏ | 16,400円 | 24,600円 |
| ~2,000㎏ | 32,800円 | |
| ~2,500㎏ | 24,600円 | 41,000円 |
| ~3,000㎏ | 49,200円 |
参考資料:2023年5月1日からの自動車重量税の税額表(出典:国土交通省)
表の通り、普通乗用車は料金区分が多く、500㎏ごとに料金が上がる仕組みなのに対して、8ナンバー車は料金が1,000㎏ごとに上がるので、金額が上がりづらくなっています。
つまり、8ナンバー車を利用することで、重量税を節約できることがほとんどです。
ただし、車両の用途によって、同じ8ナンバーでも重量税額が違う場合があります。
自賠責保険料は普通車サイズだと高くなる
8ナンバーの自賠責保険料は、通常よりも高くなるケースが存在します。
以下は、ナンバー種類別(車種別)の自賠責保険料の比較表です。
※24か月(2年)分の自賠責保険料を比較しています。
| 車種 | 8ナンバー | 自家用乗用車 |
|---|---|---|
| 3輪以上の普通自動車 | 19,980円 | 17,650円 |
| 軽自動車 | 11,290円 | 17,540円 |
参考資料:自動車損害賠償責任保険基準料率(出典:損害保険料率算出機構)
普通車がベースの8ナンバー車は、保険料が普通乗用車のよりも高めに設定されています。
対して、8ナンバーの軽自動車に関しては、11,290円と、通常と比べ、かなり安い金額設定となっています。
このように、全ての車種で自賠責保険料が高くなるわけではないという点も押さえておきましょう。
印紙代は8ナンバーでも変わらない
印紙代にはナンバーの種類は関係なく、通常通り車種(普通自動車・軽自動車など)によって金額が異なってきます。
ベースとなる車両で金額が決まるので、車の設備や用途の違いによって金額が変わることはありません。
業者に車検を依頼した場合、利用した工場によって、以下のように金額が若干異なります。
| 工場種別(車検を受ける場所) | 印紙代 |
|---|---|
| 指定工場 | 1,800円 |
| 認証工場 | 2,300円 |
参考資料:登録・検査手数料一覧表(出典:国土交通省)
上記の金額は、ほんの一例です。車検時の印紙代に関して、さらに詳しく知りたい方は以下を参照ください。

8ナンバーを取得するメリット
この章では、8ナンバーを取得・利用するメリットを紹介していきます。利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
主なメリットは以下の通りです。
- 普通乗用車よりも自動車税が安い
- 小型貨物車よりも車検期間が長い
それでは順番に解説していきます。
普通乗用車よりも自動車税が安い
8ナンバー車の大きなメリットの1つは、自動車税が安い点が挙げられます。
8ナンバーの自動車税は、普通乗用車と比べてかなり安い金額設定になっており、区分によっては、5,000~20,000円ほどの金額差があります。(排気量によって価格差は変わります。)
以下は、8ナンバー・普通乗用車の自動車税の金額比較表です。
| 排気量 | 自家用8ナンバー(2019年9月30日以前に新規登録) | 自家用8ナンバー(2019年10月1日以降に新規登録) | 自家用乗用車(2019年9月30日以前に新規登録) | 自家用乗用車(2019年10月1日以降に新規登録) |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 5,000円 | 5,000円 | 10,800円 | 10,800円 |
| 1,000cc以下 | 23,600円 | 20,000円 | 29,500円 | 25,000円 |
| 1,000越~1,500cc以下 | 27,600円 | 24,400円 | 34,500円 | 30,500円 |
| 1,500超~2,000cc以下 | 31,600円 | 28,800円 | 39,500円 | 36,000円 |
| 2,000超~2,500cc以下 | 36,000円 | 34,800円 | 45,000円 | 43,500円 |
| 2,500超~3,000cc以下 | 40,800円 | 40,000円 | 51,000円 | 50,000円 |
| 3,000超~3,500cc以下 | 46,400円 | 45,600円 | 58,000円 | 57,000円 |
| 3,500超~4,000cc以下 | 53,200円 | 52,400円 | 66,500円 | 65,500円 |
| 4,000超~4,500cc以下 | 61,200円 | 60,400円 | 76,500円 | 75,500円 |
| 4,500超~6,000cc以下 | 70,400円 | 69,600円 | 88,000円 | 87,000円 |
| 6,000超cc以上 | 88,800円 | 88,000円 | 111,000円 | 111,000円 |
参考資料:自動車税(種別割)の税率(出典:大阪府庁)
普通乗用車との金額差はかなり大きいので、利用すれば、年間の維持費を大幅に節約できます。
小型貨物車(4ナンバー)よりも車検期間が長い
8ナンバーは毎回2年ごとの車検なので、小型貨物車(4ナンバー)よりも車検期間が長いです。
そのため、車検に関する手間が少なく、利用がしやすいメリットがあります。
ただ、車検までの間隔が大きいと、使用中の予期せぬトラブルや故障もあることは念頭に置いておきましょう。
長く安心して使用するためには、定期的なメンテナンスを欠かさないことが大切です。
小型貨物車(4ナンバー車)の車検について、詳しく知りたい方は、以下を参照ください。

8ナンバーを取得するデメリット
先述のようなメリットもあれば、デメリットも存在します。
8ナンバーを取得・利用する主なデメリットは、以下の通りです。
- 整備・メンテナンス費用が高額になりやすい
- 任意保険の対象としていない保険会社が存在する
- 普通乗用車よりも初回車検までの期間が短い
それぞれ順番に解説していきます。
整備費用が高額になりやすい
8ナンバー車の1つ目のデメリットは、整備費用が高額になりがちな点です。
特殊な車両構造の点検、特殊設備の整備・メンテナンスを行うため、普通乗用車よりも費用が高くなりやすいです。
整備に対応できる業者も少なく、車検基本料が高めに設定されていることも少なくないので、車検費用全体が高額になる場合も多いです。
任意保険の対象とならない場合がある
2つ目のデメリットは、8ナンバー車を保険の対象にしていない保険会社が存在する点です。
一部の保険会社では、以下の理由で8ナンバー車を保険対象外としています。
- 保険料を算出することが困難(設備・用途が全く異なる場合もあるため)
- 省庁から加入基準に関して厳しい指導を受けている
ベースの車両が同じハイエースでも、キャンピングカーと介護車両では設備が異なります。
そのため、車両ごとに異なる保険料を算出することが難しく、断る保険会社が多いというわけです。
一般的に保険対象車として扱われるのは、以下の5つです。
- 普通乗用車
- 小型乗用車
- 軽乗用車
- 小型貨物車
- 軽貨物車
上記が対象になることがほとんどのため、8ナンバー車のような特殊車両を利用する場合は注意が必要です。
任意保険の手続きを進める前に、利用予定の業者に保険加入できるかどうかを事前に確認しておきましょう。
8ナンバー車の用途に特化した車両もあるので、視野を広げて業者を検討するのがおすすめです。
普通乗用車よりも初回車検までの期間が短い
普通乗用車(3ナンバー車)と比較して、8ナンバーは初回車検までの期間が短いです。
普通乗用車は新規検査から3年後なのに対し、8ナンバーの場合は新規検査から2年後なので、普通乗用車よりも1年短く、車検までの準備期間が短く感じる方も多いと思います。
「3年後だと思って準備していなかった」という事態にならないように、2年間でしっかり車検を受ける準備をしておきましょう。
※新車検査時から次に受ける車検までの期間を「初回車検までの期間」とします。
※初回車検以降は、8ナンバー・普通乗用車ともに「2年ごと」です。
8ナンバーを取得する4つの手順
ここでは、8ナンバーへの変更・登録を検討している方のために、取得する手順を解説していきます。
以下の4つに分けて解説していきます。
- ①:8ナンバーの取得条件を把握する
- ②:8ナンバーの取得に必要なものを用意する
- ③:8ナンバー仕様車に構造変更する
- ④:運輸局か軽自動車検査協会でナンバー変更手続きを行う
それでは順番に解説していきます。
①:8ナンバーの取得条件を把握する
8ナンバーを取得するには、設備や構造面の条件をクリアする必要があります。
設備内容の詳細は用途ごとに異なるため、以下では、構造面に関する主な条件について解説していきます。
【8ナンバー取得の基本条件】
- 特殊設備が運転席以外に存在していて、その面積が一定以上であること
- 特殊設備の面積が総床面積の半分を超えること
- 積載スペース(荷台)と運転席に仕切りや障壁があること
上記の要件のほかに、用途によってさまざまな条件があります。詳細は以下から確認可能です。
②:8ナンバー取得に必要なものを用意する
8ナンバーの取得には、以下のものが必要になります。構造変更・手続きの前に用意しておきましょう。
【8ナンバー取得に必要なもの】
- 車検証
- 自動車検査票
- 点検整備記録簿
- 自賠責保険証明書
- 認印
- 申請書(2号様式)
- 手数料納付書
- 自動車重量税納付書(必要ない場合あり)
- 自動車税種別割納付証明書
- 委任状(申請を代行してもらう場合)
車検業者に依頼する場合は、必要なものを確認しておき、車検整備の当日までに用意しておきましょう。
自分で申請手続きを行う場合は、上記の必要物を用意して、運輸支局・軽自動車検査協会に向かいましょう。
③:8ナンバー仕様車に構造変更する
必要なものを準備した後は、整備工場で構造変更を行います。
ユーザー車検を利用する場合、車検手続きとともに、構造変更の手続きなどを全て自分で行う必要があるため、手間がかかります。
業者に依頼する場合、車検整備と同じタイミングで構造変更することも可能です。
その後の手続きも代行してもらえて、手間をかけずに、車検・構造変更を完了できるので、最もおすすめな方法です。
④:運輸局・軽自動車検査協会でナンバー変更手続きを行う
車検業者に依頼する場合は、業者がナンバー変更も代行してくれます。
しかし、ユーザー車検利用の場合は、自分で変更手続きをする必要があります。
変更手続きの際は、運輸支局・軽自動車検査協会の窓口にて、以下を提出します。
- 窓口に用意されている申請書(その場で記入)
- 住民票
- 車検証
- ナンバープレート
- 自動車保管場所証名書(車庫証明)
- 自動車税申告書(もしくは軽自動車税申告書)
- ローン購入の場合は所有者(ローン会社など)の委任状
車検終了後に手続きを行い、新しいナンバープレートを購入すれば完了です。古いナンバープレートは窓口にて返却します。
8ナンバーの車検に関するよくある質問
この章では、8ナンバーの車検に関して多く寄せられていた質問に答えていきます。
以下の質問が特に多数でした。
- 8ナンバー車の高速料金は?
- 8ナンバー車の維持費は通常よりも高いですか?
- 8ナンバーのキッチンカーは車検に通りますか?
それぞれ順番に解説していきます。
8ナンバー車の高速料金は?
結論から言うと、通常の料金と変わりません。
8ナンバーは、用途ごとに様々な車種を使用しますが、ナンバーの違いによって、高速料金が変動することはありません。
高速料金は、以下の5つの車種区分で金額が異なります。
- 軽自動車・二輪
- 普通車
- 中型車
- 大型車
- 特大車
参考資料:高速料金道路簡易料金表(出典:NEXCO西日本)
8ナンバーの維持費は通常よりも高いですか?
8ナンバーの維持費は、通常よりも高くなります。
理由は以下の通りです。
【8ナンバーの維持費が高い理由】
- 整備費用が高額になりやすい
- 特殊設備のメンテナンス費用が高い
8ナンバーは特殊設備の整備・メンテナンスの費用が高額になりやすく、維持費が高額です。
対して、普通乗用車よりも重量税・自動車税が大幅に安いので、整備費が高額にならなければ、年間維持費が安くなる可能性はあります。
8ナンバーのキッチンカーは車検に通りますか?
8ナンバーのキッチンカーでも車検に通すことができます。
キッチンを積んだ状態でも車検を依頼することができ、車検項目の安全基準を満たしていれば、車検に合格することができます。
車検の流れ自体は通常の車検と変わらないので、十分に点検・整備してから車検に臨みましょう。
ただ、一般的な車検業者では整備が不可能な場合もあるため、キッチンカーの車検整備に対応している業者を探す必要があることには注意が必要です。
まとめ
内容を簡単におさらいしていきます。当記事では、以下の内容について解説しました。
- 8ナンバー車の基本知識
- 8ナンバーの車検期間は2年
- 【比較表】8ナンバーと普通乗用車の(3ナンバー車)の車検費用
- 8ナンバーを取得するメリット
- 普通乗用車よりも自動車税が安い
- 8ナンバーを取得するデメリット
- 整備費用が高額になりやすい
- 任意保険の対象とならない場合がある
- 普通乗用車よりも初回車検までの期間が短い
- 8ナンバーを取得する4つの手順
- ①:8ナンバーの取得条件を把握する
- ②:8ナンバー取得に必要なものを用意する
- ③:8ナンバー仕様車に構造変更する
- ④:運輸局・軽自動車検査協会でナンバー変更手続きを行う
8ナンバーを取得・利用すれば、車検時の法定費用が一部安くなる・自動車税が安くなるメリットがあります。
対して、整備・メンテナンス費用が高額になるリスクや、任意保険に加入できないケースがあるなどのデメリットも存在します。
すでに利用している・利用を検討している方は、8ナンバー車の用途が、車の使用目的に沿っているかどうかを改めて考えたうえで、使用することをおすすめします。